※本記事にはプロモーションが含まれています。
夜は一日の終わりを締めくくる、大切なリラックスタイムです。しかし、多くの人がつい寝る直前までスマホやタブレットを触ってしまい、結果的に寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりしています。スマホから発せられる光や、SNS・動画の刺激は、私たちの脳や体にとって予想以上に大きな影響を与えています。本記事では、スマホを置いて過ごす夜のリラックス習慣について、その重要性、実践方法、効果、そして続けるコツを詳しくご紹介します。
1. スマホを置くことの大切さ
複数の研究では、就寝前のスクリーン使用が睡眠の質を低下させる可能性が示されています。スマホやパソコンの画面から出るブルーライトは、眠りを促すホルモンの分泌を抑え、体内時計のリズムを乱すといわれています。その結果、深い睡眠(ノンレム睡眠)が減少し、翌日の集中力や判断力、感情の安定性にも影響を与えます。
さらに、SNSや動画コンテンツは情報量が多く、感情を刺激するため、脳が興奮状態になりやすくなります。この状態では「寝よう」と思っても、脳はまだ活動を続けており、寝つきが悪くなります。こうした状況が続くと、慢性的な寝不足、日中のだるさ、集中力の低下、イライラしやすくなるなど、生活全体に悪影響を及ぼします。
一方で、寝る前にスマホから離れると、脳と目の緊張が和らぎ、心拍数や血圧が自然に下がります。結果的に、入眠がスムーズになり、翌朝すっきり目覚めやすくなります。
2. スマホを置く時間を決める
効果を感じるためには、「寝る○時間前にはスマホを置く」という明確なルールを作ることが大切です。いきなり長時間やめるのは難しいため、まずは30分前から始め、慣れたら1時間前、1時間半前と徐々に延ばしていきましょう。
例えば、23時就寝の場合、22時30分にスマホの電源を切り、充電器にセットして別の部屋に置く、というルールを作るだけでも効果があります。ポイントは「物理的に手元から離すこと」です。視界から消えることで、無意識に手を伸ばしてしまうのを防げます。
また、スマホを置く時間を「お風呂上がり」「歯磨き後」など、行動の区切りと結びつけると、習慣として定着しやすくなります。
3. スマホの代わりになる過ごし方
スマホを置いた後、手持ち無沙汰にならないように、代わりの行動を用意しておくと続けやすくなります。以下はおすすめの過ごし方です。
- 紙の本や電子インク端末での読書:視覚への刺激が少なく、物語や知識に没頭することで自然に眠気が訪れます。
- 軽いストレッチやヨガ:筋肉をゆっくり伸ばすことで血行が良くなり、体温が少し下がるタイミングで眠気が強くなります。
- アロマキャンドルやディフューザー:ラベンダーやカモミール、ベルガモットなどの香りは、リラックス効果が高く睡眠を促します。
- 落ち着いた音楽を聴く:ジャズ、ボサノバ、アンビエント音楽など、テンポがゆったりした曲が理想的です。
- 日記や感謝ノートを書く:一日の出来事を振り返ることで、心が整理され安心感が生まれます。
- 温かいハーブティーを飲む:カフェインレスのカモミールやルイボスティーは心身を落ち着かせます。
ポイントは、五感を心地よく刺激する習慣を選ぶこと。照明を落とし、温かい飲み物や香りを取り入れることで、脳と体が「休息モード」に切り替わります。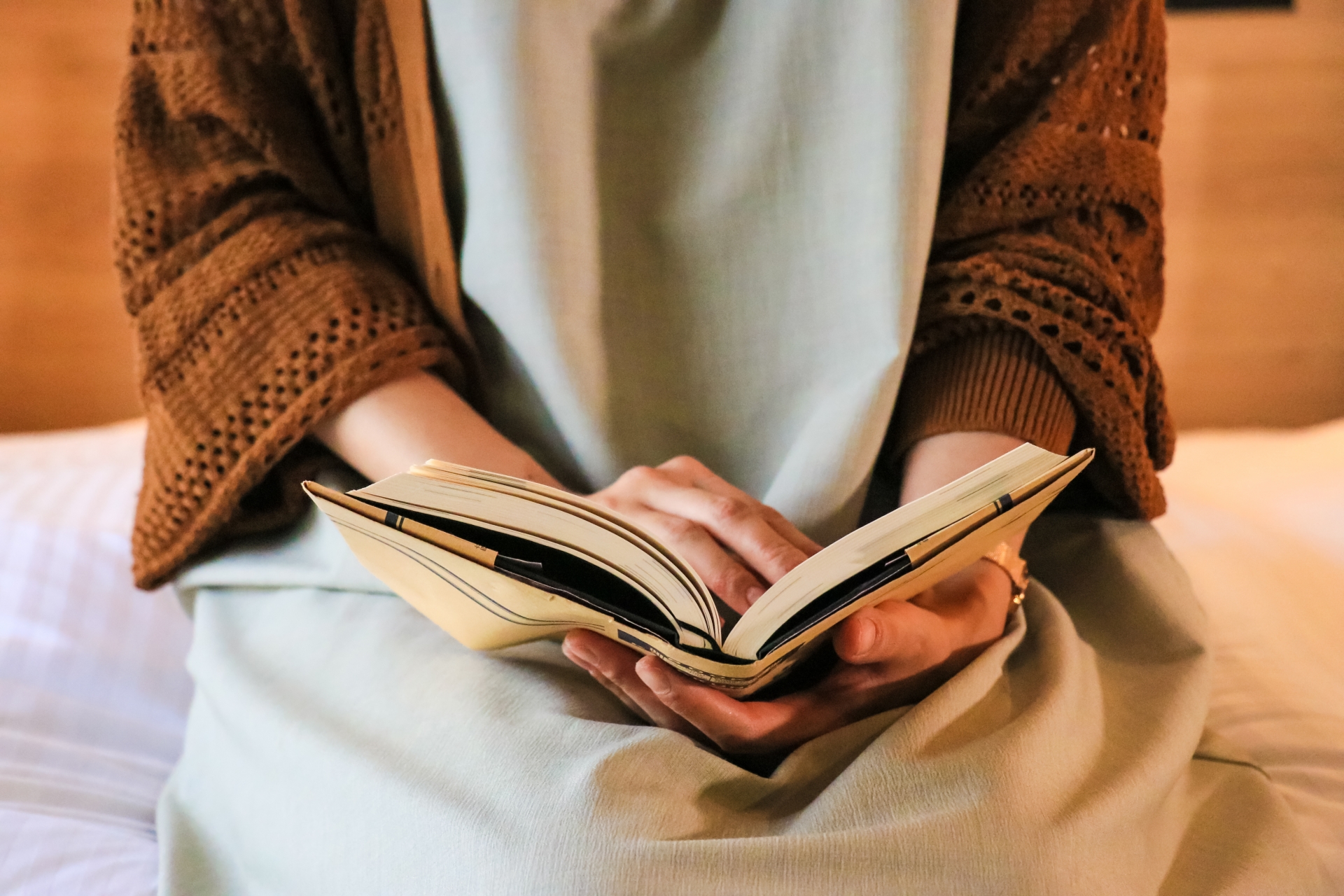
4. 環境を整える
スマホを置く時間をより快適に、そして充実したものにするためには、寝室や過ごす場所の環境づくりが欠かせません。照明は、暖色系で明るすぎないものを選ぶのがポイントです。間接照明やキャンドルライトを活用すると、光がやわらかく広がり、心と体が自然にリラックスモードへ切り替わります。特に電球色やオレンジ系の光は副交感神経を優位にし、眠気を促してくれます。一方、白色や青白い光は脳を覚醒させる作用があるため、就寝前には避けましょう。
香りの演出も効果的です。アロマディフューザーでラベンダー、サンダルウッド、カモミールなどを漂わせれば、自然と深呼吸が促され、心拍数が落ち着きます。香りは嗅覚を通して直接脳に届き、気分や自律神経の状態に大きく作用しますので、好みに合わせて選ぶとより効果的です。
寝具にもこだわりましょう。通気性や肌触りの良いコットンやリネン素材は、一年を通して快適な睡眠環境を保ってくれます。シーツや布団カバーの色を落ち着いたトーンにすることで視覚的にも安心感を得られます。さらに、部屋の室温はやや涼しめ、湿度は40〜60%が理想です。エアコンや加湿器を活用して調整すると、深い眠りをサポートしてくれます。
もし寝室以外の空間で過ごす場合も、照明・香り・温度の3つを意識することで、スマホを置いた時間をより心地よいリラックスタイムに変えることができます。
5. 習慣化のコツ
スマホを置く時間を一時的な取り組みで終わらせず、生活の一部として習慣化するにはコツがあります。まず大切なのは「誘惑を物理的に遠ざける」こと。スマホは充電器ごとリビングや玄関など、寝室から離れた場所に置きます。ベッドサイドに持ち込まないだけでも、つい手を伸ばしてしまうリスクが大幅に減ります。目覚ましはアプリではなく、アナログの時計を使うとさらに効果的です。
次に「代わりの楽しみを用意する」ことも重要です。スマホを置いた後の時間を、楽しみながら過ごせるようにします。例えば、「お風呂 → スキンケア → 軽いストレッチ → ハーブティー → 読書」という流れを毎晩同じ順番で行うと、脳が「この後は寝る時間だ」と認識しやすくなります。これがいわゆる「就寝ルーティン」です。
さらに、行動を記録するのもおすすめです。手帳やスマホ以外の記録ツール(壁カレンダー、専用の睡眠ノートなど)に「スマホを置いた時間」を書き込むことで、自分の頑張りが見える化され、モチベーション維持につながります。最初は週に3回でも構いません。少しずつ頻度を増やすことで、無理なく定着します。
また、家族と一緒に取り組むのも効果的です。「22時以降は家族全員スマホオフ」などルール化すれば、協力し合いながら続けられます。
6. 心と体への効果
スマホを置いて過ごす夜は、想像以上に多くのメリットをもたらします。まず、睡眠の質が向上します。深い眠り(ノンレム睡眠)が増えることで、翌朝の目覚めがスムーズになり、一日をエネルギッシュに始められます。また、日中の集中力や判断力、記憶力も向上し、感情の安定にもつながります。
さらに、自律神経のバランスが整い、心拍数や血圧が安定することで、ストレスが軽減されます。ストレスホルモンの分泌が減るため、心が穏やかになり、イライラや不安感が減少します。加えて、寝る直前までスマホを見ないことで目や肩、首への負担が減り、慢性的な眼精疲労や肩こり、首こりの予防にもなります。
そして何より、自分自身と向き合う静かな時間を持てるのが最大の魅力です。日々の出来事や感情を整理する時間は、自己理解を深め、幸福感を高めます。スマホに奪われていた時間を、自分のために使えるようになることで、生活全体がより豊かに感じられるでしょう。
まとめ
スマホを置く時間を意識的に作ることは、睡眠の質を高め、翌日のパフォーマンスを向上させるだけでなく、心の安定や健康にも直結します。ポイントは無理なく続けられる仕組みを作ることです。最初は寝る30分前からでも効果があります。徐々に時間を延ばし、自分に合ったリラックス習慣を見つけましょう。
静かな夜の時間は、まるで自分へのご褒美のようなもの。小さな習慣の積み重ねが、やがて大きな変化をもたらします。今日から少しずつ、スマホを置いて心地よい夜を過ごす習慣を始めてみませんか?


